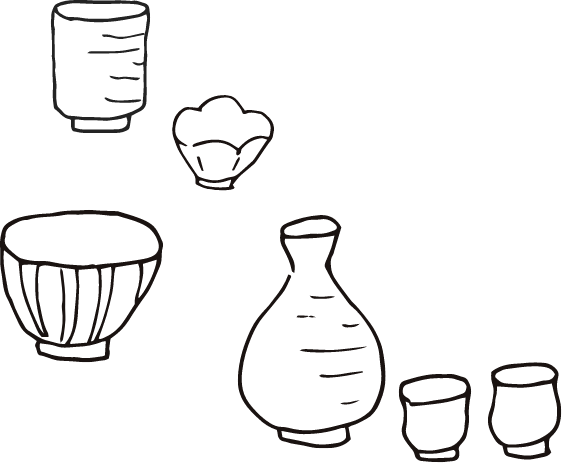金龍堂 大国寿郎作 梨地肌虫喰提手鉄瓶
| 作品名 | 金龍堂 大国寿郎作 胴体銘 梨地肌虫喰提手鉄瓶 |
| ジャンル | 鉄瓶 |
| 作品について | 最近は、野球の大谷翔平が愛用している事でも注目を集めている鉄瓶ですが、実は長い歴史を持っています。 そして、その時代ごとに様々な名工が誕生して、独自の世界観を作り上げていきます。 中でも有名なのは、「龍文堂」という工房です。 創始者は丹波国亀山藩士の家に生まれた四方龍文(生1732年(享保17年)?没1798年(寛政10年))で、1764年(明和1年)頃から京都の東洞院付近で蝋型を用いた鋳造技術で鉄瓶などを製作して生計を立てていました。 この頃の龍文は、号を金寿泰(きんじゅ やすし)と名乗っています。鋳造の「鋳」の字を分解すると「金寿」となる事から、鋳金家としての心意気と覚悟を感じる号と言えるでしょう。 2代目龍文となった嫡子の四方安之助(初代安之助)は、父の名を自らの号として「龍文堂」と名乗ります。ここから鉄瓶を巡る文化の最盛期へ向かって、数々の名工が独自の技法を編み出していきます。 そういった大きな流れの中で、大阪の鋳金家、鋳物師として台頭したのが大國家です。鋳金作品を手がける以前には、大砲を鋳造して財を成したという記録もありました。 しかし、江戸の世になって次第に戦は減り、それに伴って大砲の需要も減少しました。時は江戸後期、陶磁器の隆盛と共に茶湯の文化もまた、その栄華を極めます。 この頃、大國家は茶席で用いられる風炉など様々な金工品を手掛けています。栢斎(二代 大國藤兵衛)は大宮御所に造営された茶室「秋泉亭」の造営に伴い、秩父宮の御下命を受けて御用御釜を献上したほどの名工です。 この人物は、今回の鉄瓶を手掛けた大國寿郎の父です。 寿郎は、父から釜師としての技術と基本を、そして京都で名を馳せた龍文堂の四方安之助から鉄瓶に特化した蝋型の技術を学んでいます。 本格的に鉄瓶の製作を手がける様になってからというもの、寿郎の人気に火をつけたのは漢詩や花鳥風月といった煎茶趣味の図案を鉄味の良い素地と融合させた点でしょう。 こちらの作品では、過度な装飾は敢えて施さず、鉄味の良さを引き立たせている点に、茶道への造詣も深い寿郎ならではの「侘び寂び」を感じますね。 寿郎の作には「大國」「寿郎」や自身が創設した「金龍堂」といった銘が確認できます。 寿郎の作品と混同されやすい銘としては「大國造」「大國製」が主な物ですが、こちらは父の栢斎をはじめとする、「大國藤兵衛」を継いだ名工たちが主に使用した銘となります。 |